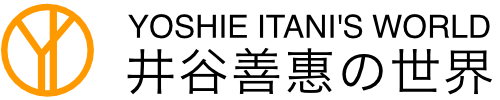髭受皿付カップ&ソーサー 瓢池園製
2011.06.02
写真は明治の初めごろに作られた瓢池園製髭受けカップ&ソーサーである。
髭受けカップ&ソーサーというのは、カップの中の液体を飲むときに口髭が汚れないようにしたものである。縁の内側に薄い磁平板を渡し、そこに半円を開けて、髭を磁平板に乗せて半円部から珈琲ないしは紅茶を飲む。すると、髭が液体に浸かることなく、この穴から飲むことが可能となる。
もともと髭受けがついた日本からの輸出磁器皿は17世紀後半から18世紀前半にかけて、東インド会社の注文に応じて作られた。明治時代に輸出された本品のカップの場合は、あきらかにその縁の内側の部分は髭受けといってよい。しかも、髭受けの真ん中の部分にくぼみがあり、鼻に当たらないようにという凝りようである。
裏には製造者名として「瓢池園造」とある(写真3)。この瓢池園により描かれた雀に盛り上げの白菊という意匠は、明治の初期には人気だったのか、ノリタケ・ミュージアム蔵の「色絵盛上菊雀文皿(井口昇山工場製 1884-1890年)」とほぼ同じであり、瀬戸の陶工で、陶磁器の輸出も幅広く行っていた加藤春光(二代目 1881-1958)も同じ意匠を様々な食器に描いている。
瓢池園とは、東京都江東区(旧深川区東森下町)に所在した絵付け工場のことで、創立者は、明治6年のウィーン万国博覧会事務局御用掛を務めた河原徳立(1844-1914)である。徳立は明治27年ごろには当初の雀に白菊といった和風から洋風絵付けに転じた。 その後、明治39年には瓢池園の事業を長男太郎に託し、徳立は二男のいる京都にて「ふ くべ焼」として陶磁器製造を始める(京都瓢池園)。また、長男太郎は明治31年頃には、取引先であった森村組(現在のノリタケカンパニー)の絵付け工場の名古屋での集約化に伴って名古屋に移っている。東京絵付けを代表する徳立の考えからすれば、東京から名古屋への移動はまさに都落ちで、瓢池園は名古屋での集約化に最後まで抵抗した最大規模の絵付け工場といわれている。
瓢池園は集約後森村組に吸収されていくが、徳立の教えは、長男太郎、二男次郎だけでなく、三男の三郎にも受け継がれた。
三郎は徳立の父方の親戚である百木家の養子となり、百木三郎として東洋陶器社長(現在のTOTO)となった。そしてその息子(すなわち徳立の孫)春夫は、日本の高級磁器を代表する大倉陶園の八代目の社長となっている。
大倉陶園は、森村組の創業者の森村市左衛門を支えた大倉孫兵衛が大正9年に長男和親と共に「よきが上にもよきものを」と私財をなげうって東京都荏原郡六郷村(現在大田区)に作った会社である。現在は横浜市戸塚にあり、その工場は昭和時代から続く規模のさほど大きくないものであるが、今も天皇家や各皇族方にも食器等を納入している。河原家と大倉家は姻戚関係にあった。
百木春夫は大倉陶園において社長というより、名デザイナーとして知られ、一輪のバラを皿に描いたシリーズなどは今でも大倉陶園を代表するデザインである。
はじめてこのカップの縁の内側についた磁器の板のようなものを見た人にはその用途の見当がつかないだろう。しかし、これが17世紀後半の輸出伊万里髭皿の流れを受け継ぎ、瓢池園という日本の近代陶磁器の中心ともいうべき河原=大倉の教えを今に伝える作品であることを考えるとき、このカップの中に日本の輸出磁器の歴史がつまっているといえる名品である。