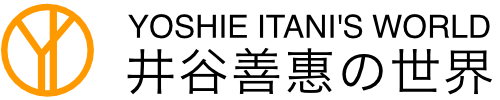器用と不器用の間にあるもの
2012.01.09
美術史としての工芸を研究していると、現代の工芸家の先生方にお話をお聞きするチャンスやアトリエを拝見させていだたけることもある。その際に常に感嘆、または感動するのが先生方の技のたくみというか、器用さである。先生方の「器用」さは、もう人間が可能な業を到達して神の域に入っているのではと思うことが多々ある。
芸術家というものは、もちろん技だけではなく、創造力も不可欠なのであろうが、多くの工芸はまずは技術の習得が先に来る。
写真は截金砂子がご専門の月岡裕二先生が2002年に日展で特選を取られた「月下・想」である。月岡先生のお仕事をぶりを拝見すると、人間はこんなことができるのだ。というか、これは人間にしかできない仕事なのかもとただただ感動である。
作業をしていないときの月岡先生が発せられる言葉は江戸っ子のきっぷの良さで、なんだか先生と話していると祭囃子が聞こえてきそうな江戸の下町の職人をほうふつさせるのだけれど、その作業は科学者が最新の器具を使っても不可能なぐらい精緻なものである。
月岡先生に限らず、工芸の先生方はもちろん、それぞれの分野については巧みであるはずで、何の技も能力もない自分と比べるのははなはだおこがましいのであるが、、いまだかつて器用だといわれたことのない自分を振り返り、器用と不器用というのはどこが違うのか考え込んでしまうときがある。
工芸の先生方は子供のころから器用だったという方々が多い。器用だから工芸の道に進まれたのか、もともとのDNAに器用というのがあり、その使い道はいろいろあるけれどたまたま工芸の道に進まれただけなのか、、その辺はよくわからないのだが、わかっているのは自分はどう間違っても工芸の道に進むどころか、普段の仕事さえすべてにおいてはなはだく不器用だという事実である。そんな自分が神業に近い器用さを持つ工芸の先生方とお話をするということそのものがすでに先生方に対して失礼千万な気もするが、ひたすら謙虚に先生方の作業に感じ入り、ありがたくお話を聞く時間を至福の時と心得る。
聞いたところで自分が器用になれるわけでもないのだが、ただ一つ言えることは、人の能力を決めるのは結局のところ、器用、不器用の差ではなく、どれだけ集中してその仕事に打ち込めるかだと先生方の話を聞いて学ぶことができたということだ。
先日もガラスの白幡明先生のアトリエを訪ねて、先生の磨かれたガラスが赤子の肌のような柔らかさと温かさを持っているのを実際に触って感じて、「器用さ」とはとほうもなく繊細な執念だと感じた。